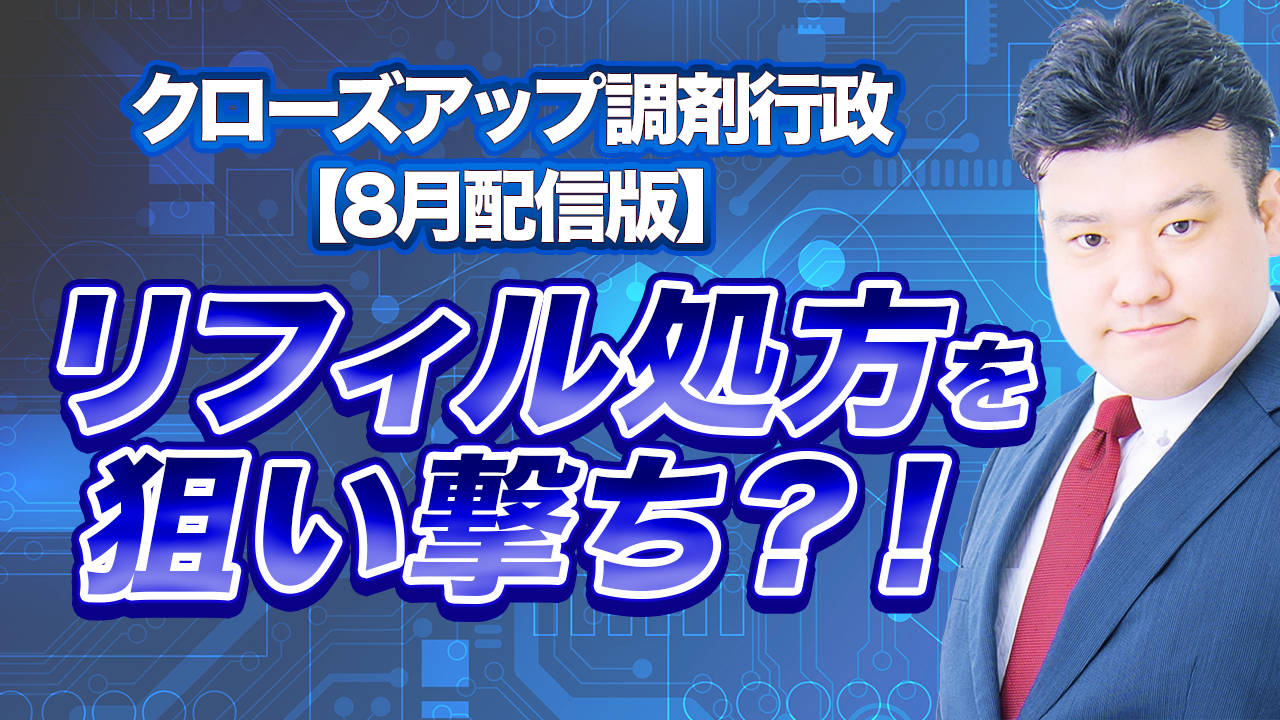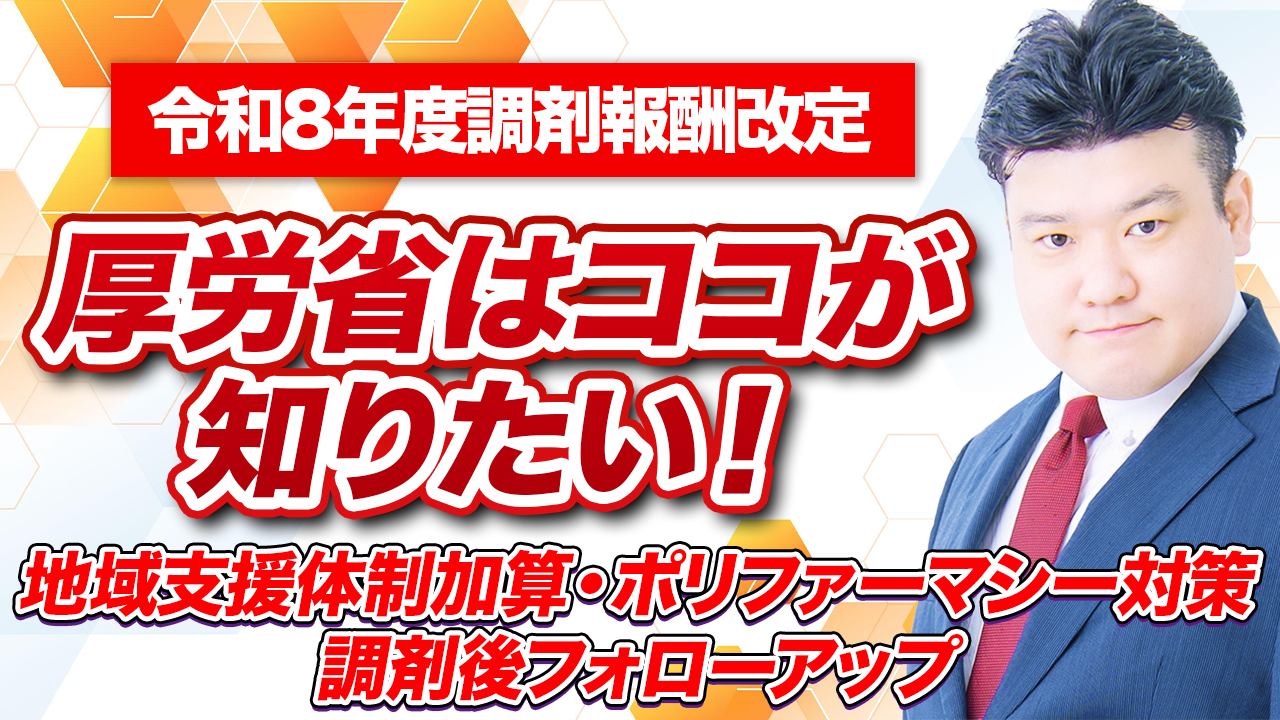前回記事に引き続き、2024年度調剤報酬改定の影響を検証する「結果検証調査」の内容を紹介します。今回は、「調剤報酬改定の影響」に関する調査項目の具体的な変更点を分析し、次期改定に向けた国のメッセージと、薬局に求められる対応を解説します。
<他の調査紹介記事>
※本記事に関するご質問等、個別のご相談は薬局経営者研究会の会員企業様に限り無料で承っております。
興味がある方はぜひご入会を検討ください。
関連YouTube
調剤報酬改定の影響に関する調査票の概要
「調剤報酬改定の影響」に関する調査は、『かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査』として2年に1度実施されています。
今回の令和7年度調査では、前回調査令和5年度調査と比較して、調査票に多くの変更点が加えられています。
これらの変更点から、国が「かかりつけ機能含む調剤報酬改定」をどのように評価し、次期改定に向けて何を重視しようとしているのか、その狙いについて仮説を立てて読み解いていきます。

▼原文資料
「オンライン服薬指導」は削除、「服薬管理指導」が追加へ!「かかりつけ薬剤師」は大きな変更なし
まずは調査票の全体像をつかむために、細かな設問に入る前に章構成の変化を確認します。見出しレベルで何が増減・再編されたかを押さえておくと、このあと章ごとの変更点を読むときに狙いが見えやすくなります。
令和5年度調査では9章が独立して「オンライン服薬指導の実施状況」でしたが、令和7年度ではこれを独立章から外し、9章を「服薬管理指導等」に再編。一方、「かかりつけ薬剤師」の章立てと設問内容は両年度で大きな変更はありません。
このあと、各章ごとに具体的な変更点(追加/削除/修正)を解説していきます。

「1章:貴薬局の状況」の変更点
地域の所在区分(特別区等)を追加
新たに所在区分(特別区/政令指定都市/中核市/その他)が新設され、前回までの法人形態の細分類は削除されました。回答負担を抑えつつ地域特性を軸に分析できる設計への整理と読み取れます。背景には、医療資源の偏在や患者動線の違いが取組の成果に影響し得るという仮説があると考えられます。

なお、現行の調剤報酬で地域差が反映されているのは、医療資源が少ない地域に限った基本料の特例が中心で、その他の点数に地域差は大きくありません。今回の所在区分追加は、調査結果次第で地域差に応じた評価(点数や実績基準値の調整)を検討する余地も示唆していると受け止められます。
保険調剤売上の割合 追加
新たに「薬局売上に占める保険調剤の割合」を問う設問が加わりました。これにより、薬局がどの程度、保険調剤を主な収入源としているかが可視化されます。

本設問追加の背景には、地域支援体制加算の要件に48薬効群のOTC医薬品取り扱いが組み込まれたことが影響している可能性があります。OTCを扱うかどうかは売上構成に直結し、“調剤専業型”とOTCや雑貨を含む“調剤併設型”の違いを把握する上で重要な視点です。こうしたデータは、かかりつけ薬剤師の活動や服薬管理指導、残薬解消といった各種取組の傾向を読み解く手がかりとなり、今後の制度設計において評価の在り方に議論が広がるきっかけになるかもしれません。
後発医薬品関連項目 追加
後発医薬品の調剤割合や関連加算の算定状況に関する複数の設問が新たに追加されました。具体的には、調剤報酬算定上の後発医薬品調剤割合(6月1か月間)や、供給停止医薬品への臨時的な取扱いの有無、後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い医薬品が減算対象となるかどうかなどを確認する内容です。さらに、後発医薬品調剤体制加算の種類や、在宅薬学総合体制加算の算定状況についても尋ねられます。

これらの設問は、後発医薬品の使用促進政策の進捗や、供給制限下での現場対応の実態を把握することを目的としていると考えられます。特に、供給停止や切替制限が続く中で、減算や加算の要件をどの程度満たせているのかを確認することで、今後の制度運用や要件見直しの議論につなげる狙いが見えます。
調査結果によっては、供給制限時の例外取扱いの範囲や、後発医薬品使用割合の基準値、減算要件の厳格化などが、次期改定で検討される可能性があります。
主な処方元医療機関の種別・外部情報共有 ICT活用状況 削除
令和5年度調査では、薬局が最も多く処方箋を受け付けた医療機関について「診療所か病院か」「在宅療養支援の届出区分」を尋ねる設問や、他の薬局や医療機関、多職種との情報共有・連携で活用しているICTツール(メール、電子掲示板、地域医療情報連携ネットワーク等)を確認する設問がありました。
令和7年度調査では、これらの項目が丸ごと削除されています。おそらく、別の設問や既存の届出情報から、受付件数の多い医療機関の種別や連携状況を把握できるため、重複する調査を省いたと考えられます。


「2章:貴薬局の体制」の変更点
導入機器・システム導入状況、他薬局との連携体制 追加
薬局の体制をより具体的に把握するため、導入機器やシステムの状況を尋ねる設問が追加されました。対象は、レセプトコンピューター、電子薬歴システム、薬剤情報提供文書作成支援ツールの3種類で、支援ツールについてはQRコード・音声コード・点字といった機能の有無まで細かく確認する構成です。これにより、薬局が患者への情報提供にどのような手段を用意しているか、また業務支援のための環境整備がどの程度進んでいるかを把握することができます。

さらに、夜間・休日対応のために医療機関や訪問看護ステーション、他薬局と連携体制を整えているかどうかを問う設問も追加されました。こうした連携は、緊急時の対応力や地域包括ケアの一翼を担う上で欠かせない要素です。今回の設問追加は、薬局の内部体制と外部連携の両面から現状を可視化し、将来的な評価や制度設計に活かす狙いがあると考えられます。
調剤報酬改定による収益影響・業務転換状況の確認 削除
令和5年度調査では、診療報酬改定による影響として、薬局の保険調剤収益が増減したか、また薬剤師業務が「対物中心から対人中心」へどの程度転換したかを尋ねる設問がありました。さらに、転換が進んでいる場合には、その具体的な取組内容(処方内容のチェック、服薬指導、継続的服薬管理、残薬対応、ポリファーマシー対策など)を複数回答で把握する構成となっていました。

しかし、令和7年度調査ではこれらの設問がすべて削除されています。業務転換や収益影響の把握については、他章の具体的取組項目や加算算定状況などからも一定程度推測できるため、調査の重複を避ける意図があった可能性があります。
「3章:麻薬調剤等」の変更点
麻薬処方患者へのスケール評価実施状況 頻度区分追加・未実施理由の把握 追加
麻薬が処方された患者に対するスケール評価(NRS等)に関して、2つの変更が行われました。
1つ目は、実施状況に「すべての患者」「半数以上の患者」「一部の患者」「実施していない」という頻度区分が新たに追加されたことです。これにより、評価の実施率をより定量的に把握できるようになりました。

2つ目は、スケール評価を「実施していない」場合の理由を尋ねる設問が新設されたことです。「必要性を感じない」「対象患者が少ない」「医師が実施している」など、未実施の背景を明らかにすることで、今後の疼痛管理や麻薬適正使用の改善に向けた課題抽出が可能になります。
無菌製剤処理件数に関する設問 削除
令和5年度調査では、TPN(中心静脈栄養)、麻薬、抗悪性腫瘍剤の無菌製剤処理件数および加算の算定件数を把握する詳細な設問が設けられていました。さらに、対象薬剤ごとの件数や、TPN・麻薬・抗悪性腫瘍剤以外で無菌製剤処理件数の多い薬剤を順位付けして回答するなど、実態を細かく掘り下げる構成でした。

しかし、令和7年度調査ではこれらの設問がすべて削除されています。背景には、令和6年度改定で無菌製剤処理加算の対象に「麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合」が追加されたことが影響している可能性があります。対象範囲が明確化されたことで、従来のように詳細な件数や薬剤別内訳を調査票で把握する必要性が薄れたと考えられます。
無菌製剤処理体制の選択肢を詳細化
令和7年度調査では、無菌製剤処理の体制に関する設問が詳細化され、従来は一括されていた「無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備」が、それぞれ個別の選択肢として分解されました。これにより、薬局ごとの設備整備状況をより正確に把握できる構成になっています。

背景には、令和6年度改定で在宅薬学総合体制加算2の要件に「無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備」が盛り込まれたことがあると考えられます。加算要件との整合性を高めつつ、無菌調製に関する具体的な設備の有無を把握することで、在宅業務の質や安全性確保の実態をより精緻に評価する狙いがうかがえます。
「4章:感染症対策等」の変更点
感染症対応・ゾーニング関連設問の整理
令和5年度調査では、新型コロナウイルス感染患者(疑い患者を含む)の来局時におけるゾーニング状況や、別室・動線分離などの具体的な対応方法を詳細に問う設問が設けられていました。
しかし令和7年度調査では、こうした個別設問は削除され、代わりに感染症対策全般を問う設問の中に「感染症疑い患者と一般外来患者の動線を分離している」という選択肢が新たに追加されました。
この変更は、感染症法上の新型コロナの位置づけ変更や、薬局現場での対応が平常運用へと移行したことを背景に、特定感染症として詳細なゾーニング状況を把握する必要性が薄れた可能性があります。今後は新型コロナに限らず、幅広い感染症リスクを想定した標準的な感染症対策の一環として動線分離を位置づけ、継続的な感染防止策の実施状況を把握する狙いがあると考えられます。


検査キット・新型コロナ治療薬の取り扱い状況 設問整理
令和5年度調査では、「薬事承認された検査キット」と「新型コロナ治療薬」について、それぞれ別設問で詳細を確認していました。検査キットでは抗原定性検査や新型コロナ・インフルエンザ同時検査の有無、治療薬では薬剤名ごとの取り扱い状況を尋ねる形式でした。
令和7年度調査では、両設問ともに選択肢が整理され、検査キットは「新型コロナ抗原定性検査」「新型コロナ+インフルエンザ同時検査」「いずれもなし」の3択、新型コロナ治療薬は「取り扱いあり/なし」の2択となりました。
背景には、令和5年3月24日付で厚生労働省より発出、同年4月1日適用の事務連絡「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて※」により、感染症流行時における検査キットや治療薬の確保・提供体制が連携強化加算の施設基準要件として明確化されたことがあります。これにより、地域での医療継続体制を支える薬局の備えが一層重視されるようになりました。
こうした経緯から、今回の設問では詳細な製品名や検査種別よりも、提供の有無そのものを把握することを優先し、調査の負担軽減と全国的な概況の迅速な集計を可能にする設計へと整理されたと考えられます。
※ 令和5年3月24日付 厚生労働省保険局医療課 事務連絡
「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」
連携強化加算の届出状況と未届出理由 追加 (設問構成を変更して継続調査)
「連携強化加算の届出状況」に関する設問が、地域支援体制加算の章から独立し、新たに感染症対策等の章に配置されました。令和5年度調査でも同様の項目は存在しましたが、当時は届出の有無に加え、施設基準のうち満たしている項目を回答する形式でした。
今回の変更では、届出がない場合に限り、満たすことが難しい施設基準を選択する形式へと整理されています。選択肢には、医療機関指定や感染症対応研修、防護具備蓄、災害・感染症発生時の医薬品供給体制、自治体からの要請対応、手順書整備など、実務上ハードルとなり得る要件が網羅されています。

この見直しは、届出阻害要因の抽出を目的としている可能性が高く、今後の加算要件緩和や支援策の検討材料として活用されることが想定されます。結果として、地域における感染症・災害対応力の底上げを図るための基礎データが得られる構成に改められたといえます。
「5章:かかりつけ薬剤師に関する取組」は変更なし
今回の調査では、「かかりつけ薬剤師に関する取組」の設問項目に変更は見られません。設問構成や内容は令和5年度調査を踏襲しており、評価の視点や調査対象の範囲も同様です。
このことから、制度運用や評価基準の大きな方向性は現時点で安定していると考えられます。今後の制度改定に向けた新たな分析は、既存のデータ蓄積や経年変化の把握に重点が置かれる可能性があります。
「6章:地域支援体制加算」の変更点
休日・夜間対応体制の周知状況 追加
休日や夜間を含む開局時間外でも調剤および在宅業務に対応できる体制(輪番制を含む)の周知状況を問う設問が新たに追加されました。さらに、周知を行っている場合には、その方法(自薬局・グループHP、薬剤師会経由、行政機関経由、その他)と、周知先(住民・患者、他薬局、医療機関、訪問看護ステーション、福祉関係者、行政機関、その他)についても詳細に回答する形式です。

この設問追加の背景には、令和6年度改定で地域支援体制加算の施設基準に「休日・夜間対応体制の整備とその周知」が新たに要件として加えられたことがあります。加算を算定する薬局は、実際に対応体制を整備しているだけでなく、その存在を地域に広く周知することが求められるようになりました。今回の調査は、この要件がどの程度現場で履行されているかを把握し、運用状況を可視化する狙いがあると考えられます。
OTC備蓄・販売状況および女性の健康サポート体制 追加
一般用医薬品および要指導医薬品の備蓄・販売状況を問う設問が新たに設けられました。特に「基本的な48薬効群」の取り扱い有無や、その充足状況を細かく確認する構成となっており、さらに直近1か月間の販売実績についても尋ねています。これは、令和6年度改定で地域支援体制加算の要件に48薬効群の備蓄が盛り込まれた流れを踏まえ、制度運用の実態を把握する狙いがある可能性があります。

また、女性の健康サポートに関する体制整備状況を問う項目も新設されました。緊急避妊薬の取り扱いや、妊婦等からの服薬相談対応は、これも令和6年度改定で地域支援体制加算の要件として新たに追加されたものであり、これらの対応状況を確認する狙いがあります。さらに、外部講師を含む研修実施や健康教室の開催なども対象となっており、薬局が地域における女性の健康支援で果たす役割を可視化する内容です。こうした情報は、地域住民への支援機能の強化や、多様化する健康ニーズへの対応を評価する上で、今後の制度設計にも影響を与える可能性があります。
実績要件に関する設問 構成変更
地域支援体制加算の施設基準該当状況を問う設問が、令和6年度改定後の施設基準の並びに合わせて再構成されました。
設問内容はほぼ同一ですが、要件の順序や分類方法が改定後の基準に準じた形に整理されています。

施設基準満たすことが難しい項目 追加
地域支援体制加算では、届出を行っていない薬局を対象に、満たすことが難しい施設基準の具体的な項目を尋ねる設問が新設されました。今回の選択肢は、令和6年度改定で新たに加わった施設基準の要件を含め、すべての基準項目を網羅する構成となっています。

これにより、備蓄品目数や医療材料供給体制、麻薬管理、在宅業務対応、情報提供体制、健康サポート活動など、多岐にわたる要件について現状の達成状況をより詳細に把握可能となりました。この変更は、地域支援体制加算の普及・定着を後押しするとともに、達成が難しい要件を可視化し、今後の改善や支援策の検討につなげる狙いがあると考えられます。
「7章:残薬解消、ポリファーマシー解消・重複投薬の削減のための取組」の変更点
ポリファーマシー解消・重複投薬削減のための自薬局の取組 選択肢追加
ポリファーマシーの解消や重複投薬の削減に関する取組項目に、「電子処方箋システムの活用による重複投薬等の確認」や「オンライン資格確認システムによる薬剤情報・特定健診情報の確認」、さらに「学会や地域で開催される研修会への参加」が追加されました。

特に電子処方箋は令和5年1月から本格運用が始まったばかりであり、その活用状況を把握することは今後の制度運用の改善にも直結します。また、研修会参加については、将来的に何らかの制度要件や加算要件として義務化される可能性も考えられ、薬局のICT活用や人材育成の実態を詳細に把握する狙いがうかがえます。
ポリファーマシー解消・重複投薬削減に関する設問の見直し
令和7年度調査では、令和5年度調査で設けられていた「残薬解消」に関する個別設問が削除され、内容がポリファーマシー解消や重複投薬削減に焦点を当てた構成へと整理されました。これにより、前段の設問で実施している取り組みを尋ねた上で、阻害要因や課題に関する具体的な回答を求める形に再編されています。
阻害要因の選択肢としては、「患者・家族の理解・協力が得られない」「効果的な方法がわからない」「対応するための十分な時間が捻出できない」といった項目が新たに提示され、現場が直面する実態の把握をより直接的に行う意図がうかがえます。


地域での協議体参加者と機能状況の把握 追加
ポリファーマシー解消や重複投薬の削減に向けた地域での取り組み状況をより具体的に把握するため、「地域で協議する場合に、どのような関係者が参加しているか」を尋ねる設問が新設されました。自治体、保険者、医師会、病院・診療所関係者、薬剤師会、薬局関係者、介護・看護関係者、学識経験者など、幅広い関係者の関与状況を確認する内容となっています。

さらに、これらの関係者が参加する協議の場について、「機能していると感じるかどうか」を評価する設問も設けられました。地域での多職種連携や情報共有の実効性を測ることが狙いと考えられます。将来的には地域支援体制加算など、何らかの評価点数の施設基準要件として組み込まれる可能性も否定できません。今後の加算要件の動向を見据え、地域での協議体制を整備しておくことが重要になりそうです。
薬剤レビューと問い合わせ簡素化プロトコル活用の実施状況 追加
新たに薬剤レビューの実施状況を問う設問が追加されました。薬剤レビューとは、患者個別の情報を体系的に収集・評価し、薬物治療の有効性を最大化しつつ、副作用や重複投薬のリスクを最小限に抑えることを目的としたプロセスです。選択肢では、すべての患者への実施、特定条件患者のみ、その他、未実施の4区分で、現場の実施度を可視化します。
加えて、処方箋発行元医療機関への問い合わせにおいて「問い合わせ簡素化プロトコル」を活用しているかを問う設問も新設されました。このプロトコルは、事前に医療機関と薬局間で合意書を取り交わし、変更可能な調剤内容を明確化して問い合わせ手続きを省力化する仕組みで、地域の連携強化に寄与します。実際、大阪府豊能・三島地区では、地域薬剤師会と医療機関が連携し、プロトコルに基づく変更対応を運用しており、その詳細は前回改定時の中医協総会資料にも取り上げられています。


こうした取り組みは、将来的に地域支援体制加算や服用薬剤調整支援料等、何らかの評価要件に組み込まれる可能性があり、今から体制整備を進めておくことが望まれます。
調剤管理加算・服用薬剤調整支援料関連の設問 削除
令和7年度調査では、令和5年度調査に存在した「調剤管理加算の算定実績」や「服用薬剤調整支援料1・2の算定状況」に関する設問がすべて削除されました。具体的には、初回または2回目以降の処方箋持参時における算定回数や、未実施理由を問う設問がなくなっています。
これは、点数の算定実績を把握することから一歩踏み込み、ポリファーマシー解消に向けた行為そのものの状況を把握することに重点を移した可能性があります。調剤管理加算は前述の「薬剤レビュー」と密接に関連し、その過程で減薬の成果が得られた場合には服用薬剤調整支援料を算定できるという流れがあります。
今回は算定の有無よりも、こうした減薬・薬物適正化に向けた取組状況そのものを把握する意図が感じられます。


「8章:調剤後のフォローアップ」の変更点
調剤後薬剤管理指導料の算定阻害要因 追加
新たに「調剤後薬剤管理指導料」の算定状況や、算定できなかった理由を尋ねる設問が追加されました。
※設問内で用いられている「調剤後薬剤管理指導加算」という表記は誤りの可能性が高く、令和6年度改定で新設された「調剤後薬剤管理指導料」を指していると考えられます。

具体的には、地域支援体制加算の届出状況、対象患者の要件充足、医師や患者からの求めの有無、電話等による薬学的管理の実施、フォローアップ後の文書による情報提供の有無など、多角的な選択肢が用意されています。これにより、単なる算定実績だけでなく、算定が進まない背景や阻害要因を可視化し、制度設計や運用改善の参考にする狙いがあると考えられます。
こうした詳細な情報収集は、フォローアップ体制や地域連携の強化策、将来的な点数要件見直しの議論にも活用される可能性があります。
インスリン製剤・SU剤および吸入薬指導加算算定状況に関する設問 削除
令和5年度調査では、薬局におけるインスリン製剤やスルホニル尿素系製剤(SU剤)の調剤有無を確認する設問、さらに吸入薬指導加算の算定状況を把握する設問が設けられていました。これらはいずれも、特定薬剤や特定加算の運用実態を把握することを目的としたものです。
しかし、令和7年度調査では両設問とも削除されています。背景として、特定薬剤や特定加算の有無だけでなく、より包括的に「調剤後フォローアップ全般」の取組実態を把握する方向へ調査方針がシフトしていることが考えられます。

特にフォローアップが必要な疾患に「小児慢性特定疾病」 追加
令和5年度調査では、特にフォローアップの必要性が高い疾患として、糖尿病、ぜんそく、COPD、心不全、血栓塞栓症、認知症、精神疾患、悪性腫瘍などが列挙されていました。令和7年度調査では、これらに加え「小児慢性特定疾病」が新たに選択肢として追加されています。

小児慢性特定疾病は、疾患特性上、長期的かつ継続的な薬物療法や多職種連携による健康管理が不可欠であり、薬局による服薬状況の把握や副作用のモニタリングが重要となります。今回の追加は、成人患者だけでなく、小児患者に対するフォローアップの重要性をより明確化し、薬局の支援対象を広げる意図があると考えられます。
また、調査項目として明示的に含めることで、小児慢性特定疾病患者への対応実態を可視化し、今後の報酬評価や制度設計の議論材料とする狙いも見えてきます。
フォローアップ対象患者の属性 複数項目を追加・修正
令和7年度調査では、フォローアップの必要がある患者属性に関して、選択肢の見直しと追加が行われています。まず、「長期処方」の定義が「処方日数30日以上」から「処方日数28日以上」に変更されました。これは、28日処方を長期処方として扱う動きに合わせた調整とみられます。
さらに、次の3項目が新たに追加されました。
- 薬剤や治療に不安を持っている患者
- 新規で来局した患者
- ポリファーマシーの患者

これらの追加により、従来の疾患ベースの選定だけでなく、患者の心理的要因や薬剤数、受診・来局の経緯など、より幅広い観点からフォローアップ対象を抽出することが可能になります。特に「ポリファーマシーの患者」は、減薬や薬剤適正化の取り組みと密接に関係しており、今後の評価や加算要件にも反映される可能性があります。
フォローアップで収集する情報項目 追加
令和7年度調査では、フォローアップ時に収集する情報項目が見直され、新たに「患者の生活習慣(食生活、運動習慣、飲酒/喫煙等)」が追加されました。これにより、薬物療法の効果や副作用の評価に加えて、生活習慣が服薬状況や治療経過に与える影響をより包括的に把握できるようになります。

また、既存項目のうち「服薬期間中に保健医療機関を受診し追加された併用薬」については、「新規受診」という表現が加わりました。これは、患者が新たに医療機関を受診したケースをより明確に把握する狙いがあると考えられます。
これらの変更により、フォローアップは単なる薬剤情報の確認にとどまらず、生活背景や新規受診の有無も含めた、多角的な患者評価を行う方向に進化していることが読み取れます。
疾患別フォローアップ実施人数 追加
フォローアップの実施状況をより詳細に把握するため、疾患別の実施人数を記載する設問が新たに追加されました。糖尿病、ぜんそく、COPD、心不全、血栓塞栓症、認知症、精神疾患、悪性腫瘍、小児慢性特定疾病、その他といった疾患区分ごとに、実際にフォローアップを行った人数を報告する形式です。1人の患者が複数の疾患を有する場合は、疾患ごとにカウントすることが求められます。

さらに、フォローアップの実績が0回だった場合の理由を尋ねる項目も追加されました。「必要な患者がいない」「必要な情報が不足」「医療機関との連携不足」などの選択肢が提示され、未実施の背景を定量的に把握する意図がうかがえます。
この改訂により、フォローアップの実施率だけでなく、疾患ごとの対応状況や未実施の要因が明確になり、将来的な制度設計や評価基準の見直しにつながる可能性があります。
「9章:服薬管理指導」の内容
特定薬剤管理指導加算1・3関連 追加
令和6年度改定で新設・見直しが行われた特定薬剤管理指導加算1・3に関連する新たな設問が設けられています。これらの設問は、加算算定の有無にかかわらず、ハイリスク薬や医薬品リスク管理計画(RMP)に基づく指導の実施状況や課題を把握することを目的としていると考えられます。


設問は大きく以下の2つのテーマに分かれます。
- ハイリスク薬の服薬指導状況
実施頻度(毎回実施、用量変更時や副作用発現時のみ、実施していない等)や、加算を算定できなかったケースの有無とその理由(初回処方でない、同一処方で複数回実施、用量変更や副作用がなかった等)を詳細に確認する内容です。これにより、現場での服薬指導の実施基準や運用上の課題を明らかにしようとしていると考えられます。 - RMP(医薬品リスク管理計画)に基づく指導状況
実施タイミング(初回処方時、継続中の資料作成時等)、患者向け資料の交付・提示方法(交付、提示のみ等)、および加算算定に至らなかった理由(2回以上実施済み等)を調べています。これは、改定で新設された「特定薬剤管理指導加算3」の運用実態や、RMP資料活用の実態を把握する狙いがあるとみられます。
これらの調査は、施設基準や加算要件の充足度だけでなく、現場での指導の「質」と「タイミング」に焦点を当てている点が特徴です。今後、調査結果が加算要件や運用ルールの見直し、または算定機会拡大の検討に直結する可能性があります。
「10章:医療機関等との連携」の変更点
服薬情報等提供料3 算定阻害要因・薬局間情報提供 追加
服薬情報等提供料3に関する設問が新たに追加されました。服薬情報等提供料3は、入院前の患者に関して医療機関へ情報提供を行った場合に評価される点数であり、入院時の薬物療法の安全性確保や治療方針の適正化に寄与する重要な役割を持ちます。
新設された設問では、この点数の算定有無と、算定回数(医療機関向け、医療機関以外向け)を把握するほか、算定がない場合の阻害要因についても詳細に質問しています。阻害要因としては「医療機関から依頼がない」「対象となる患者がいない」「在宅患者であった」などが挙げられており、実務上の課題の洗い出しを狙っています。

なお、他の服薬情報等提供料に関しては算定できなかった理由を問う設問が見当たらないため、本調査では服薬情報等提供料3に焦点を当てた課題把握が重視されていると読み取れます。算定していない場合でも他薬局への情報提供回数を確認しており、医療機関連携に加えて薬局間連携の実態把握にも踏み込んでいます。
入退院時支援や退院時カンファレンス参加状況等に関する設問 削除
令和5年度調査では、医療機関との連携内容について、連携方法や情報共有方法を複数選択式で詳細に把握する設問が設けられていました。具体的には、退院時カンファレンスや服薬情報の提供、抗がん剤治療時の副作用発現時対応に関するプロトコルの有無など、多岐にわたる項目が列挙されていました。

また、患者の入退院時の連携状況や、医療機関から受け取った退院時サマリーの有無・内容(投与薬剤の記載の有無など)についても詳細に調査していました。
令和7年度調査では、これらの項目がすべて削除されており、医療機関とのやり取りに関する詳細な把握は行われなくなっています。これは、同様の情報が別の調査や制度運用の中で把握可能になった、もしくは重点を他の項目に移した可能性が考えられます。
終わりに
今回の特別調査票の変更点からは、「調剤報酬改定」の影響評価を、これまで以上に多角的かつ実態に即して把握しようとする国の姿勢がうかがえます。地域差や連携体制、後発医薬品の利用状況から、感染症・災害対応、女性の健康支援、ポリファーマシー対策、服薬管理・フォローアップまで、幅広い領域で詳細な情報収集が試みられています。
特に、加算算定の有無だけでなく、「なぜ算定できないのか」という阻害要因の把握や、「現場の取り組み内容」そのものの可視化に重きを置いた設計が目立ちました。これは単なる制度運用の確認にとどまらず、次期改定に向けて課題を洗い出し、評価体系を再構築するための布石といえるでしょう。
調査結果が公表される頃には、既に次期改定議論が本格化しているはずです。薬局としては、この調査で問われているテーマや視点を自らの現場に照らし合わせ、現時点での強みと課題を把握しておくことが重要です。制度改定は「待つ」ではなく「備える」もの。今回の変更点を手掛かりに、自局の現状把握と次の一手の検討を進めていきましょう。
まだ取り上げていない調査、後発医薬品の使用促進や医療DXなど、薬局に影響を及ぼすその他の調査項目についても順次取り上げていきます。今回の「クローズアップ調剤行政」は以上です。次号もお楽しみにお待ちください。
(作成:株式会社ネグジット総研 経営コンサルタント 津留隆幸)
弊社サービスを問題解決にご活用ください
経営コンサルティング
- 豊富なノウハウと実績を基にした経営改善支援
- 自律型人材育成・組織活性化のために必要な要素を盛り込んだ人材育成・組織活性化支援
経験豊富のコンサルタントが
伴走型で問題解決をサポート