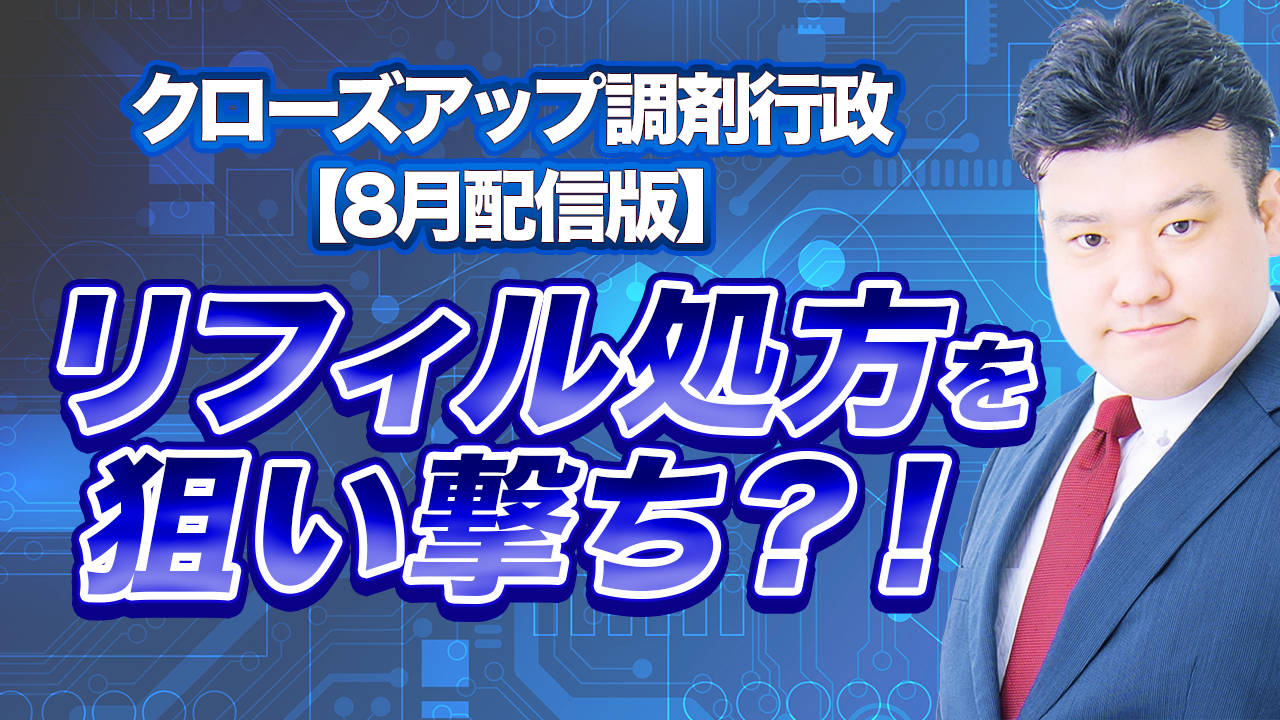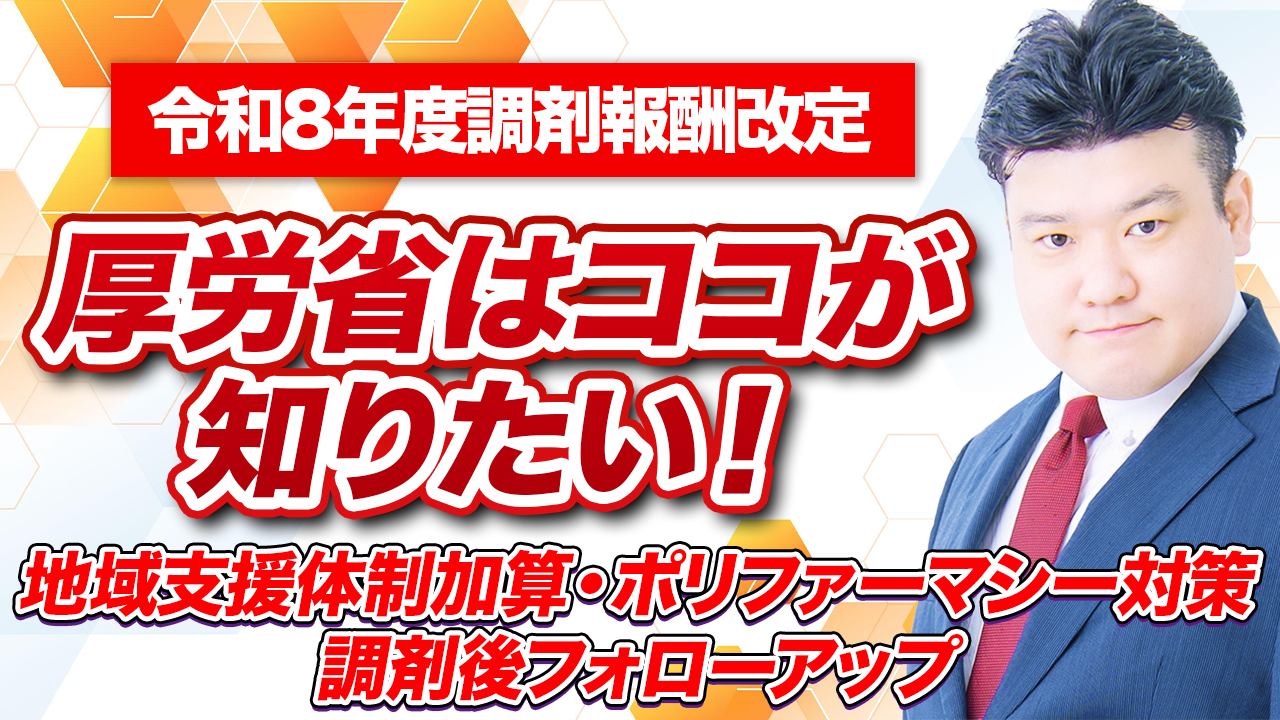2024年度調剤報酬改定の影響を検証する「結果検証調査」の概要が明らかになりました。今回の調査項目の変更点を読み解くと、厚生労働省が「リフィル処方箋の普及」と「長期処方の適正化」への関与を、薬局に対してより一層強く求めていることが鮮明に見えてきます。
本記事は「クローズアップ調剤行政」2025年8月配信版として、結果検証調査の変更点を考察するシリーズの第1弾です。今回は、調査全体の概要と、「リフィル・長期処方」に関する項目の具体的な変更点を分析し、次期改定に向けた国のメッセージと、薬局に求められる対応を解説します。
<他の調査紹介記事>
※本記事に関するご質問等、個別のご相談は薬局経営者研究会の会員企業様に限り無料で承っております。
興味がある方はぜひご入会を検討ください。
関連YouTube動画
2025年7月実施の会議・通知情報
クローズアップ調剤行政【2025年8月配信版】では、2025年7月の気になる行政動向を紹介します。
7月中に実施された調剤関連の主な会議や発出された通知等は次の通りです。
厚生労働省
- 2025年07月04日 「経済財政運営と改革の基本方針 2025」(中略)等について 他|第116回社会保障審議会医療部会
- ★2025年07月09日 診療報酬改定結果検証部会からの報告について 他 |中央社会保険医療協議会 総会(第611回)
- 2025年07月16日 外来について(その1) 他 |中央社会保険医療協議会 総会(第612回)
- 2025年07月17日 薬剤業務について 他 |中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(入院・外来医療等の調査・評価分科会)第7回
- 2025年07月23日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に向けた論点等について|厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 令和7年度第2回
- ★2025年07月23日 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて 他 |中央社会保険医療協議会 総会(第613回)
- 2025年07月24日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会及びワーキンググループの議論の進め方等について|第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
内閣府
- 無し
財務省
- 無し
※特に調剤報酬に影響が大きいと思われる会議内容に「★」印を付けています。
2025年7月の調剤行政に関するトピックスで今回ご紹介したいのは中医協総会での議論です。7月は計3回の中医協総会が開催され、次期改定の方向性を示す重要な議論が交わされました。
特に注目すべきは、★を付けた2つの議題です。
一つは、7月9日の総会で、次期改定の議論の土台となる「令和6年度(2024年度)診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」の調査票が公表されたことです。この調査は、本年8月から順次実施される予定です。
調査結果が明らかになるのはまだ先ですが、調査票の「問い」の内容から、国が改定結果の何を検証しようとしているのかを読み解くことができ、次期改定の論点について仮説を立てることが可能になります。詳細については後ほど詳細に言及します。
もう一つは、7月23日に議論された「医療DX推進体制整備加算」の要件見直しです。特に、2025年10月からのマイナ保険証実績要件について見直しの方向性が示されたほか、電子カルテ情報共有サービスへの対応に関する経過措置の延長も決定されました。これは多くの薬局の体制整備や算定計画に直結する喫緊の課題ですが、「医療DX推進体制整備加算」の詳細については本記事では取り上げません。
以降の章では、まず今回のメインテーマである「改定結果検証調査」の変更点について、7月9日の中医協総会で示された調査票を基に深掘りして考察します。
「令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)」の概要
「診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(以下、特別調査)」は、診療報酬改定の影響を把握し、次回改定の議論に活かすことを目的として厚生労働省が実施する調査です。2025年度に行われる今回の特別調査は、改定設計に直結する性格を持っています。
調査実施スケジュール
今回の令和7年度特別調査は以下のスケジュールで進められる予定です。
- 調査票の合意:2025年7月9日(中医協 総会)
- 調査の実施:2025年8月中
- 結果のとりまとめ:2025年10月
- 中医協への報告:2025年11月中旬
実施される特別調査の全体像と、薬局への影響
調査項目は、以下の5項目が調査対象として挙げられています。これらは、既に中医協総会で2025年7月9日に調査票の内容として正式に合意されたものです。
【令和7年度調査項目一覧】
① 長期処方やリフィル処方の実施状況調査
② 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査
③ 医療DXの実施状況調査
④ かかりつけ歯科医の機能の評価等に関する実施状況調査
⑤ かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査
このうち、④の「かかりつけ歯科医」に関する調査を除く4つの調査は、すべて薬局に直接関係・影響する内容です。項目も多岐に渡り、令和8年度改定に向けた“薬局への影響力”が非常に大きい内容となっています。
調査内容の変化から厚労省の思惑が読める?!
今回の特別調査を制度の評価にとどまらず、次期改定に向けた政策設計の材料そのものとして活用される点で、非常に重要です。
特に、過去にも繰り返し調査されてきた項目であっても、設問内容の変化から厚労省が何を新たに把握しようとしているのか、どのような仮説を立てているのかが読み取れるようになっています。
つまり、設問の追加・削除や文言の変更は、政策側の問題意識の反映であり、改定に向けた検討の“入口”と考えることができます。

ここから変更内容毎に、厚労省がどのような意図をもって変更をしたのかを考察していきます。
※以下、あくまでも筆者個人の考察のため、内容を保障するものではありません。あらかじめご理解の上ご覧ください。
(参考)「令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)の調査票案について」中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第74回)
『長期処方箋・リフィル処方』関連の調査票変更ポイント
リフィル処方や長期処方は、近年の診療報酬改定でも継続的に議論されてきたテーマです。今回の特別調査でも調査項目に含まれており、調査票の設問にも一部変更が加えられています。
以下に、薬局調査票を中心に変更ポイントを示しながら、それぞれの背景や意図を簡潔に考察します。
(参考)令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)長期処方やリフィル処方の実施状況調査 保険薬局票
薬局と医療機関の立地・関係性を問う設問追加
まず、回答する薬局の立地を問う設問が大きく変更されています。従来の選択肢は、住宅街・駅前等の一般的な分類でしたが、医療機関の近隣等、医療機関との物理的距離を軸とした選択肢に変更されています。
加えて、その立地に至った経緯を問う設問が追加されました。

この変更からは、リフィル処方や長期処方の実施状況が、薬局と医療機関との関係性の強さや位置関係に影響されるのではないかという、厚労省側の仮説がうかがえます。
たとえば、医療機関の近くに位置する薬局では、患者が定期的に受診する傾向が強く、リフィル処方の必要性や活用頻度が低くなる可能性もあります。一方、医療機関から離れた薬局では、患者の通院負担を軽減する手段として、リフィル処方がより積極的に活用されているかもしれません。
こうした視点を導入することで、単に「リフィル処方がどれだけ使われているか」ではなく、その活用を取り巻く背景や制約要因を把握しようとする意図があると考えられます。これは今後の改定において、地域特性や薬局の立地要因を考慮した制度設計を進める布石とも言えるでしょう。
リフィル処方・長期処方の発行元病院 機能評価種別を追加
リフィル処方・長期処方の発行元となる医療機関の機能区分を問う設問が新たに設けられています。
具体的には、「一般病院1・2・3」「リハビリテーション病院」「慢性期病院」「精神科病院」「緩和ケア病院」「診療所」など、医療機関の種類と機能に応じた選択肢が細かく設定されています。

この設問からは、医療機関の機能特性とリフィル・長期処方の発行傾向との関連性を把握しようとする厚労省の狙いが読み取れます。たとえば、慢性期医療や維持期リハビリを担う病院では、患者の病状が比較的安定しており、リフィル・長期処方が活用されやすい可能性があります。一方で、急性期を担う一般病院や精神科病院では、病態変化に応じた処方調整が頻繁に求められるため、リフィル・長期処方の活用には一定の制約があると想定されます。
また、診療所が多くのリフィル処方を発行しているかどうかを検証することで、制度の“実質的な入口”がどの医療機能に集中しているのかを分析する目的もあると考えられます。これは、今後の制度運用において、どの機能を持つ医療機関に対して重点的に制度周知・支援を行うべきか、あるいはどこにボトルネックがあるのかを見極める判断材料にもなります。
リフィル調剤件数、調剤可否に困った事例 削除
前回調査に設けられていた以下の設問が削除されています。
- 「リフィル処方箋の総使用件数のうち、調剤が完了した枚数」
- 「リフィル処方による調剤の可否判断に困った事例の有無とその理由(例:急性期疾患の薬が含まれていた/処方1回の使用期間が判断できなかった 等)」

これらはいずれも、リフィル処方箋がすでに発行され、薬局が実際に対応する“運用段階”における状況を把握するための設問でした。しかし今回、それらが調査票から除かれたという点は、単に制度の運用が落ち着いたというよりも、制度が十分に活用されていないという実態を背景にしている可能性があります。
つまり、リフィル処方箋が現場に“届いていない”という課題のほうが大きく、調剤段階の問題を問うこと自体が意味を持ちにくくなっていると厚労省が判断したとも読み取れます。実際、多くの薬局においてリフィル処方箋の受付件数は依然として限定的であり、「可否判断に悩む」といった場面が少ないのが実情です。
前回改定前後のリフィル処方箋件数の変化、薬剤師受診勧奨の有無を追加
次に、以下設問が追加されています。
- 「改定前後で最後の回の調剤を終えたリフィル処方箋の件数に変化があったか」
- 「リフィル処方箋を受け付けた際、薬剤師より受診勧奨をしたことがあるか」

1つ目の設問は、令和6年度改定で講じられたリフィル処方に関する対応策の実績数への効果検証を目的としていると考えられます。
令和6年度の改定議論では、保険者側から「生活習慣病管理料にリフィル処方の活用を要件化すべき」といった、制度の実効性を高めるための強い要望が寄せられました。特に医療費適正化の観点から、慢性疾患患者の受診間隔の適正化や服薬管理の効率化が期待されており、保険者としてはリフィル処方の積極活用を進めたいという立場が明確でした。
しかし、医療機関側の慎重な姿勢や運用上の懸念を受け、最終的にはこの要件化は見送られ、患者への制度周知など比較的“ライトな対応”にとどまりました。こうした経緯を踏まえると、この設問は、“あえて強制力を伴わせなかった改定が、現場でどの程度活用され、実際に件数の変化につながったか”を検証する意図があると読み取れます。
2つ目の設問「薬剤師より受診勧奨をしたことがあるか」は、リフィル処方の運用における薬剤師の判断と役割の実態を把握しようとするものです。リフィル処方は医師の診察無しに連続的に調剤を行う特性上、患者の状態を継続的に観察し、必要に応じて受診を促すといった薬剤師の介入が重要です。調査結果により、薬局薬剤師が“かかりつけ薬剤師機能”としての役割をどの程度果たしているかも浮き彫りになる可能性があります。
リフィル処方箋2・3回目調剤に関する医師への報告状況 追加
続いて、リフィル処方箋の2回目・3回目の医師への報告に関して、以下の設問が新たに追加されています。
- 「リフィル処方箋の2回目・3回目の調剤を行った際、患者が来局したことを医療機関(かかりつけ医)に報告していますか。」
- 「患者が、リフィル処方箋の2回目・3回目の調剤の期間に来局しなかった場合、医療機関(かかりつけ医)に報告していますか。」

これらの設問は、リフィル処方の運用における薬局と医療機関との情報連携の実態を把握することを目的としていると考えられます。
リフィル処方の制度設計上、患者が定期的に同じ薬局で調剤を受けることを前提としていますが、実際には2回目・3回目の調剤の過程で患者の行動が予測通りに進まないケースも想定されます。その際、薬局が単独で調剤行為を完結するのではなく、継続的に(特に2回目以降)医療機関と適切に情報共有を行っているかどうかは、制度の信頼性や安全性を担保するうえで重要なポイントです。
とりわけ、2つ目の設問は、リフィル処方箋の活用における“空白期間”に対する薬局の対応を問うものです。患者が来局しなかった場合、それが服薬中断による健康リスクにつながる可能性もあるため、薬局が医療機関とどのように連携を取っているかが問われています。
これら設問追加は、「リフィル処方は患者の利便性向上と医療資源の効率化に寄与する一方で、患者の自己管理能力に委ねられる側面も大きく、薬局・医療機関の連携による補完体制が不可欠である」という厚労省の問題意識を反映していると読み取ることができます。調査結果によっては、今後、リフィル処方における報告義務(あるいは評価)や情報連携体制の整備が求められる方向性も考えられます。
(医師調査)リフィル処方箋2・3回目報告の要望 追加
前項と関連して、医師を対象とした調査票にも、リフィル処方箋の運用に関する新たな設問が追加されています。
- 「リフィル処方箋の2回目・3回目の調剤における薬局からの報告について、どのようにお考えですか。」

この設問は、薬局から医師への調剤経過報告の必要性について、医師側の受け止めやニーズを把握することを目的としていると考えられます。
前項で触れたように、薬局調査票では「調剤した/しなかった」際の医療機関への報告実態を問う設問が追加されました。今回、医師調査にも連動してこの報告に関する設問が盛り込まれたことで、「薬局からの報告が本当に求められているのか」「現場の医師はどのような報告を必要としているのか」という視点からの検証が可能になります。
これは、今後リフィル処方に関する制度強化を図るにあたり、単なる“薬局側の努力義務”にとどまらず、医療機関側のニーズを踏まえた情報連携のあり方を再整理する必要性が出てきていることを示唆していると言えるでしょう。
また、仮に多くの医師が「薬局からの報告を望む」と回答するような結果になれば、リフィル処方における連携体制を強化する方向に制度が動く可能性もあります。今後、ICTの活用も視野に入れた仕組みの検討に発展していく可能性がある分野と言えます。
リフィル処方が適する状況 選択肢追加
続いて、リフィル処方が適すると考える状況を問う設問に、以下選択肢が追加されています。
- 「4.医師不足や医療資源が限られている地域での対応が求められる場合」
- 「9.対面でのフォローアップが必要な患者」
- 「10.遠距離の医療機関を受診している患者」
- 「11.副作用のモニタリングが必要な患者」

これらの選択肢の追加からは、単に「リフィル処方が可能な範囲の拡大」だけでなく、その活用が期待される場面や配慮すべき状況について、厚労省がより具体的に把握しようとしている姿勢が読み取れます。
特に、「対面フォローが必要な患者」や「副作用モニタリングが必要な患者」といった記述は、リフィル処方が必ずしもすべての慢性疾患患者に一律で適用できるものではなく、個々の患者背景に応じた運用の重要性を意識していると考えられます。
また、「医療資源の乏しい地域」や「遠距離通院」という観点は、医療アクセスの確保という課題と制度の親和性に関する探索的な意図も感じられます。
このように、今回の設問構成からは、制度の一律運用ではなく、多様な医療現場における実態とニーズを把握しようとする調査目的が見て取れます。将来的に制度をより柔軟かつ実効的に活用するための基礎的情報収集の一環と位置づけられるでしょう。
リフィル処方箋応需時の課題 選択肢追加
続いて、リフィル処方箋を受けるにあたって、課題と感じることを問う設問に、以下選択肢が追加されています。
- 「8.患者の仕組みの理解」
- 「9.医師の仕組みの理解」
- 「10.薬剤師の仕組みの理解」

これらの追加からは、制度そのものの理解度に起因する運用上の障壁に厚労省が問題意識を持っていることがうかがえます。
特に、「患者」「医師」「薬剤師」と三者すべての理解不足を選択肢として挙げている点は、リフィル処方箋の活用が単独のプレイヤーの努力では進まない制度であることを改めて示しています。実際、前回の改定でも生活習慣病管理料(医科点数)に「患者への制度周知」の対応が要件に追加された背景には、制度理解の広がりの乏しさがあったと考えられます。
また、薬局現場から見れば、リフィル処方箋応需時に「患者が制度そのものを理解していないため、説明に時間を要する」「医師からの理解が不十分で、調剤時に確認を求められる」といった日常的な実務負担も報告されています。
今回の選択肢追加は、こうした制度の“実務的な機能不全”を可視化し、今後の制度改善や周知施策に向けた基礎データを収集する意図があると読み取れます。
現場における制度の浸透度を測るための調査項目として、極めて実務的かつ現実に即した視点が盛り込まれた設問と言えるでしょう。
リフィル処方関連の患者から受けた相談の内容 選択肢追加
続いて、患者から患者からリフィル処方に関する相談を受けた内容を問う設問に、以下選択肢が新設・変更されています。
- (新設)「1.リフィル処方箋を使用したい」
- (変更)「1.リフィル処方箋の制度内容を知りたい」→「2.リフィル処方がどのような仕組みになっているのかを知りたい」

この変更からは、リフィル処方に対する患者の関心の高まりとともに、実際の制度運用に対する理解度や不安の実態を把握したいという意図が読み取れます。「仕組み」という表現の導入は、制度の有無や利用経験の有無だけでなく、その背後にある制度設計や運用方法まで視野に入れた情報収集を試みているものと考えられます。
こうした動きは、今後の制度運用の現実的なサポート策の検討にもつながる可能性があります。たとえば、特定薬剤管理指導加算3や選定療養(ロ)のように、「初回の制度説明」を評価対象とする診療報酬点数の新設が検討されることも十分考えられるでしょう。制度を正しく理解しないまま運用することによるトラブルや不安を防ぐうえでも、薬剤師による丁寧な説明を報酬として評価する枠組みは、制度定着に向けた有効な一手となります。
(医師調査)リフィル処方のデメリット懸念 設問追加
関連して、医師調査に「リフィル処方のデメリットとして懸念していること」を問う設問が追加しています。選択肢には、以下の内容が盛り込まれています。
- 患者の症状の変化や副作用の見逃し
- 患者が調剤を受ける際の負担の増加
- 処方箋の不正利用
- 患者の服薬管理への不安
- 薬剤師との連携への不安
- その他(自由記述)
- 特に懸念はない

これらの設問は、リフィル処方の制度拡大にあたって、医療現場が抱える懸念や運用上の課題を可視化する意図があると考えられます。とりわけ、「症状変化や副作用の見逃し」「服薬管理への不安」といった項目は、患者の状態把握が診察間隔の延長により難しくなることを懸念した声と見られます。
一方で、前項でも触れたように、薬剤師によるリフィル制度の丁寧な説明や、患者へのフォローアップの工夫(服薬指導、来局管理、医療機関への情報提供)などを通じて、こうしたリスクを一定程度カバーする余地もあります。実際、薬剤師調査側では患者の理解不足を課題とする設問が追加されており、医師と薬剤師の連携強化が、制度の安全な運用に向けた鍵になることを、厚労省側も意識していると考えられます。
終わりに
今回の記事では、「令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)」のうち、特に“長期処方・リフィル処方”に焦点を当て、設問の変化から厚労省の問題意識や次期改定に向けた視点を考察しました。現場での実施状況にとどまらず、立地や医療機関の機能区分、情報連携の実態までを掘り下げる調査設計からは、制度の運用実態を精緻に捉えようとする姿勢が見えてきます。
リフィル処方という制度が、利便性の向上や医療資源の効率化といった期待に応えるには、制度そのものの理解促進と、薬局・医療機関・患者の三者連携が不可欠です。今回の調査は、その基盤となる実態把握に向けた重要な一歩といえるでしょう。
まだ取り上げていない調査、後発医薬品の使用促進や医療DXなど、薬局に影響を及ぼすその他の調査項目についても順次取り上げていきます。今回の「クローズアップ調剤行政」は以上です。次号もお楽しみにお待ちください。
(作成:株式会社ネグジット総研 経営コンサルタント 津留隆幸)
弊社サービスを問題解決にご活用ください
経営コンサルティング
- 豊富なノウハウと実績を基にした経営改善支援
- 自律型人材育成・組織活性化のために必要な要素を盛り込んだ人材育成・組織活性化支援
経験豊富のコンサルタントが
伴走型で問題解決をサポート